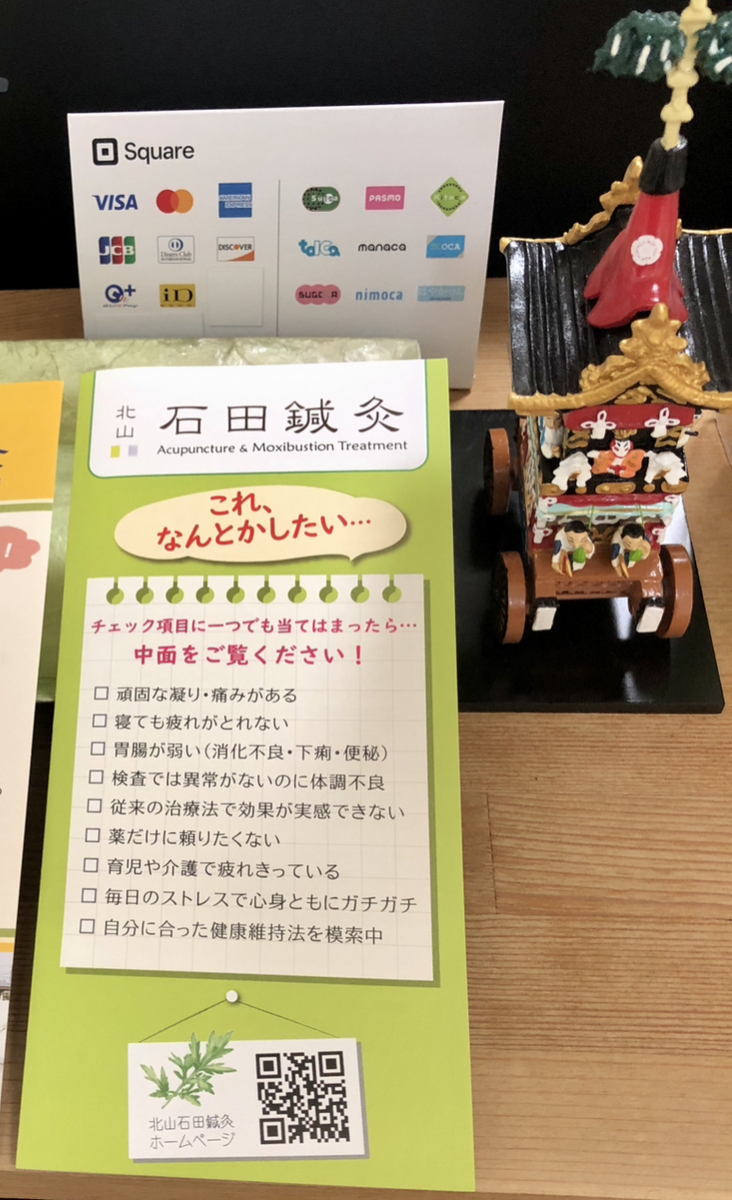11月の三連休の中日、楽しみにしていた「大枝山(おおえやま)古墳群 秋の一般公開」に愛車ヤマハ セロー250を駆って行って参りました。
桂坂を目指して国道9号線をひたすら西へと向かいます。なだらかな丘陵地に美しい公園が作られており、そこに隣接する谷の部分にこの古墳群はありました。この桂坂から南へ広がる桂川右岸流域の向日市、長岡京市の平野には大小の古墳が点在しており、京都に遷都されるより数百年以前から豪族が勢力を持ち、肥沃な土地と豊富な水を用いた農耕が盛んだったことが伺えます。

「大枝山古墳群」の造営年代は、古墳時代の終末期6世紀後半から7世紀初頭で、比較的小型の円形の古墳「円墳」が20基以上集まっています。「桂坂古墳の森保存会」のたくさんのボランティアスタッフの方々がにこやかに出迎えて下さいました。

開放された門をくぐると、美しい紅葉の森の中を縫うように道がついており、こんもりと盛り上がったたくさんの墳丘に出会うことができました。20数基の古墳のうちの3基だけが内部の石室を公開しており、それぞれの開口部には考古学に詳しいベテランのスタッフさんがおられて詳しく説明して下さいました。

ここにあるのはすべて当時の中央政府「ヤマト王権」とのつながりを誇示する巨大な「前方後円墳」ではなく、規模も形状も比較的質素なものばかりです。(質素とは言え、築造には莫大な時間と費用がかかったはずですが。)スタッフさんの説明によると、「村長さんレベルのお墓」とのことでした。

6世紀終盤から7世紀と言えば、いわゆる飛鳥時代に当たり、3世紀後半から約300年間に渡って北海道、東北の一部を除くほぼ日本全土を巻き込んだ一大ムーブメント「古墳時代」が終わりを告げる頃です。そして外来の仏教が日本の思想、政治、経済の中心に据えられる、まさに時代の変革期に相当します。大きさも形も造営年代も法隆寺の西にある「藤ノ木古墳」によく似ており、その影響を感じさせます。

昼食に持参のサンドイッチをスタッフの方々がお弁当を食べている辺りから少し離れた所でとった後、その横で開かれていた誰でも参加できる「勾玉(まがたま)作り」に挑戦してみました。蝋石(ロウセキ)という柔らかな素材を小型の鉄ヤスリで削って整形します。子どもたちが主なお客さんでしたが、私も小一時間黙々と取り組んでみました。
やってみると意外に難しく、削りすぎると後戻りできないので慎重にならざるを得ません。他の大人の参加者の方たちは冗談まじりに気楽に楽しんでやっておられる様子でしたが、私は「もと美術部の意地!」で本気を出して取り組みました。

その甲斐あって、自分でも感心するほど良い作品に仕上がりました。係の方に見せると、「これは今日一番の出来や!」と言って頂き、人が集まってきました。通す紐も分けて頂き、それを首から提げて、紅葉の小径を有頂天になって帰りました。